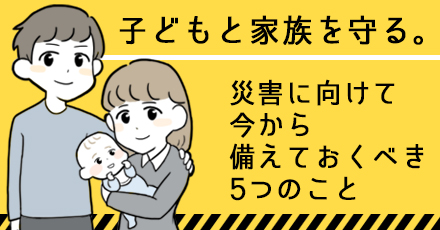突然の赤ちゃんの発熱や急な高熱が出たとき、慌ててしまい心配になりますよね。
特に赤ちゃんや子どもは、急に熱が上がることが多く、珍しい事ではありません。
さっきまで元気に遊んでいたのに、急にぐったりして熱が上がったということもあります。
夜中や休日に発熱する場合もあり、病院に連れて行っていいのか迷います。
「赤ちゃんの発熱の原因を知りたい!」
「赤ちゃんが急に高熱を出したらどうしよう…」
「熱があるときの離乳食のおすすめは?」
赤ちゃんの発熱の原因にはいろいろな理由が考えられるので、赤ちゃんの発熱とその対処法について、正しい知識を得ておくことで、いざというときの対応ができます。
- 赤ちゃんの発熱
- 赤ちゃんに多い感染症と病気
- 高熱のときの9つの対処方法
- 高熱時におすすめの離乳食
この順番で詳しくご紹介していきます。
赤ちゃんの発熱時に慌てないために、またすぐに対処できるように役立つと嬉しいです。
目次
赤ちゃんの発熱

赤ちゃんが発熱したからといって、それが病気とは限りません。
もともと赤ちゃんは体温が大人より高く、体温調節機能も未発達のため、熱が上がりやすいのです。
40度近くまで、ぐんと熱が上がる赤ちゃんも少なくありません。
「何度から?」と赤ちゃんの体温で病院に行くかどうか判断することもありますが、まずは、普段の平熱を把握しておきましょう。
授乳後や遊んでいるときは体温が上がりやすいので、寝ているときや落ち着いているときに体温を測っておくとよいです。
赤ちゃんはどんな時に熱がでるの?
赤ちゃんを抱っこしていると、いつもより体や顔が熱いかな?と感じる時があります。
しかし、食欲もあり元気もあるのであれば、部屋が暖かすぎる・洋服を着せすぎている・眠いなど、風邪や病気以外の原因の可能性もあります。
逆に、赤ちゃんに元気なく、ぐったりとしているときや、食欲がないとき、機嫌が悪くずっと泣いているときなどは、病気や風邪などを疑いましょう。
赤ちゃんにも多い感染症や病気の症状

赤ちゃんの発熱のときに、熱以外にどのような症状が確認できますか?
何か当てはまるものがないか、どのような感染症や病気があるのかみていきましょう。
水疱瘡(みずぼうそう)
水疱瘡はヘルペスウィルスの一種である水痘・帯状疱疹ウイルスによって起こります。
全身に小さな粒上の発疹ができる病気で、発病の仕方が2種類あるのも特徴です。
一つ目は、38~39度の発熱があり、体や顔に発疹が出てくるもの。
二つ目は、熱が出ずに、体に発疹が出てきて感染していることに気づくもの。
発疹は、赤くなっており虫刺されのように見えます。
少しずつ膨れてきて、中に水を含んだ水疱(すいほう)が3日目くらいにできます。
1週間後には黒いかさぶたになり落ちていきますが、うっすら痕が残ります。
水疱瘡はかゆいだけで、他には重い症状がない病気です。
周りに移らないように、登園や外出を控えなければなりませんが、赤ちゃんが元気であるのであれば、子どもたちがいない公園などで軽くお散歩をしても大丈夫です。
突発性発疹
突発性発疹とは、生後6か月から2歳ごろまでにみられる高熱のでる病気です。
発熱以外には下痢の症状が伴うことがあります。
38.5度以上の高熱が続くのですが、機嫌がよく食欲がある赤ちゃんも多いようです。
3日程高熱が続きますが、その後熱が引いていき、半日くらいたつと、胸やお腹、背中に発疹ができ、顔や手足にも広がります。
突発性発疹は2種類のウイルスにより感染します。
2つとも一生に一度しか感染しないのですが、2度突発性発疹が起こる可能性があるということです。
感染していても、発疹がでない不顕性感染の赤ちゃんも多く、典型的な症状がでる赤ちゃんは全体の半分といわれています。
また、突発性発疹は熱性けいれんを引き起こしやすい病気です。
高熱に痙攣と、ダブルパンチでご家族も本当にびっくりして慌てますが、怖いものではありません。
後ほど、熱性けいれんの対処法についてもご紹介しますね。
アデノウイルス感染症
アデノウイルス感染症は、いわゆる「のどかぜ」です。
喉を見てみると赤く腫れていて、扁桃に白い苔のようなものがべったりとくっついている場合は急性扁桃炎、喉全体が赤い時には急性咽頭炎と呼ばれています。
治るのには4日から1週間ほどかかるのですが、発熱も一緒に長引くことが多く辛抱が必要です。
扁桃炎を繰り返す赤ちゃんや子どももいて、扁桃を取ることを薦められることもあるのですが、医者により取らなくてもよいという人もいるので、小児科や耳鼻科などで相談してから決断するとよいでしょう。
ヘルパンギーナ
ヘルパンギーナは夏風邪の代表です。
最近では、1年中みられるようになってきて、幼児や小学生にに多くみられます。
症状は高熱と喉の痛みで、突然高熱がでることもあります。
ヘルパンギーナは喉の上の部分に口内炎を引き起こし、食べ物を飲みこみづらくなります。
赤ちゃんの食欲がない、ご機嫌が悪いようであれば、喉の奥を一度みてみましょう。
インフルエンザ
冬に発症するインフルエンザ。
今年も大流行しています。
症状としては、突然の高熱、咳や鼻水、喉の痛み、頭痛、筋肉痛などがあります。
急に高熱になるので、熱性けいれんを引き起こしやすいのも特徴です。
まれに、インフルエンザは脳症を起こします。
インフルエンザ脳症は1歳をピークに、0歳から5歳までに起こるのがほとんどです。
脳症がおこってしまうと、治療法がないために半数近くがなくなり、また後遺症を残してしまうことがあります。
麻疹(はしか)
はしかは昔、生命にかかわる病気でしたが、最近では軽症化してきています。
しかし、はしかを発病すると、回復までには2週間ほどかかります。
感染後10日から14日間の潜伏期間があり、発熱からの高熱、せき、鼻水、結膜炎などが起こります。
鼻水と、せきと目やにで顔がグチャグチャになるほどです。
4日目くらいに一旦熱が下がります。
またすぐに高熱になるのですが、この下がったときに、口の中に小さな斑点(コプリック斑)ができ、これを確認してから「はしか」と判断されます。
はしかは、中耳炎、肺炎、下痢を起こすことがあります。
さらに、はしかにかかった1000人に1人は脳炎になります。
脳炎は、脳の中までウイルスが入り込み、炎症を起こしている状態です。
予防接種もあるので、医療機関で予防対策をしっかりとしておくと安心ですね。
川崎病
これは発見した小児科医の川崎富作さんの名まえをとり名付けられた病気です。
症状は、ピンク色の目、口紅を塗ったような真っ赤な唇、様々な形の発疹、首のリンパの腫れ、手の甲や足の甲の腫れが特徴で、この症状を発見したら川崎病を疑いましょう。
発熱は高熱で7日から10日ほど続きます。
2週間以上の高熱が続く場合には、心臓に病気を残すことがあるので、定期的に通院することや入院することもあります。
以前は死亡例もありましたが、現在では治療法が確立されているので死亡例はほぼありません
高熱以外の症状で、いくつか思い当たるものがあれば、早めに受診することをおすすめします。
熱中症や熱射病、脱水症
高温の中に長時間いたために起こる様々な症状を、すべて熱中症といいます。
軽いものは、体の一部のけいれんなどがあるのですが、重度になると熱射病と呼ばれる状態になります。
熱射病の特徴は、急な頭痛、意識の混乱、意識が薄い、そして急な高熱と汗がとまることがあげられます。
38度くらいの発熱でも汗が出ていないようであれば、生命にかかわることもあるので注意が必要です。
まずは、涼しい場所に移動し、洋服を脱がせて、皮膚の表面を濡れたタオルで拭き、濡れたままにしておきます。
手や新聞などで風あてている状態で、救急車を呼びましょう。
そのままにせず、病院で処置をしてもらいます。
発熱を伴う赤ちゃんの病気には色々なものがあり、ご紹介したものは一部です。
他にも色々な病気の可能性もあるので、ただの発熱じゃないと感じたらしっかりと記録しておきましょう。
赤ちゃんが高熱を出した時の対処方法

発熱以外の症状を確認する
発熱以外の赤ちゃんの症状から考えられる病気を判断することもできます。
耳を触ると嫌がったり泣いたりするときは、中耳炎。
咳や鼻水、くしゃみが出ているときは、風邪や気管支炎。
高熱なのにご機嫌で食欲があるときは、突発性発疹。
リンパの腫れ、発熱と同時に顔や体、手足に発疹があるときは、風しん。
喉が赤く炎症しているときは、急性咽頭炎や急性扁桃炎、インフルエンザや風邪。
口の中に白い斑点ができ、全身に発疹がでるときは、はしか。
このように症状から色々な病気を判断することもできるので、まずは落ち着いて赤ちゃんの様子をしっかりと見てみましょう。
時間外でも病院に行ったほうがよい症状
高熱が出たとき、すぐに病院へ行く必要ではないことが多いのですが、次のような症状がみられたときには、すぐに病院に連れて行くようにしてください。
- 5分以上のけいれんがあるときや、けいれんを繰り返しているとき。
- 呼吸が苦しそうで息づかいもあえぐようなとき。
- ぐったりとしており、意識がはっきりとないとき。
- 顔色が青白くなり、手足が冷たいとき。
お母さんがひとりで赤ちゃんを見ているときは、チャイルドシートに乗せることができない場合もあります。
そのときは、救急車を呼ぶ、もしくはかかりつけ医に連絡するなど早めに対応することが必要です。
夜間や休日でも、救急病院へ行ってください。
これ以外の症状で病院を受診するか迷っているときには、小児救急電話相談に連絡し、対応を教えてもらうとよいでしょう。
連絡先は「#8000」です。母子手帳への記載や携帯電話などに登録しておくと、いざというときに役に立つかもしれません。
体温や症状を記録しておく
赤ちゃんの発熱や、嘔吐や下痢などの症状を記録するようにしておきましょう。
病院に行った際に、症状を伝えることで診断しやすくなります。
病院では、いつから発熱したのか、機嫌や食欲の有無、咳や鼻水の有無、下痢や嘔吐の有無、けいれんの時間や回数の有無などを聞かれます。
しっかりと伝えられるように準備しておくために記録しておきましょう。
震えているときの対処法
熱が上がっているときにガクガクと赤ちゃんが震えることがあります。
これは「悪寒」と呼ばれており、ひきつけと間違われることもあります。
ひきつけやけいれんは、意識がなくなりますが、悪寒は意識があり会話をすることもできます。
ガクガクしているときは、まず名まえを呼んで、反応があるか確かめましょう。
おうちでできる対策としては、衣服やお布団を暖かいものにし、首回りなどを温めるようにしてください。
熱が上がりきると悪寒は止まります。
今度は暑くなってくるので、衣服やお布団を調節しながら様子を見ていきましょう。
ひきつけや痙攣があるときの対処法
熱がぐんとあがるときに、ひきつけや痙攣がおきることがあります。
初めての風邪になる赤ちゃんが多く、10人に1人の割合で発症するので身近なものなのです。
何も知らないと、急なけいれんにお母さんもお父さんもパニックになります。
正しい対処法を知っておく必要があります。
まず、ひきつけや痙攣が起こったら、仰向けに寝かせた状態で、顔を横に向けてあげましょう。
これは胃の中のものの逆流が器官に詰まり窒息するのを防ぎます。
以前までは、舌を噛むから口に何か詰めなさいということを言われていましたが、現在は、それも窒息などの原因になりかねないので、そのまま何もしないことが鉄則です。
そのあとは時計を確認し、何分くらい痙攣が続くか計ります。
赤ちゃんがひきつけ・けいれんしている前で、何もせずに冷静に時間を計るのは本当に辛く耐えがたいものです。
しかし、その時間や赤ちゃんの様子(手足の動き、白目をむいている、泡をふく、おもらしをする)などを、
確認し、病院で医師に伝えることは大切なのです。
初めてのひきつけや痙攣をおこした場合には、できるだけ早めに病院に連れていきましょう。
連れていく途中で、再度ひきつけやけいれんを起こす場合もあります。
チャイルドシートに乗せる時には嘔吐やおもらしで汚さないように、バスタオルを敷いておいたほうがよいです。
ひきつけや痙攣の時間が5分以上続いており、呼吸が苦しそうで顔が青白くなっている場合は、救急車を呼ぶ必要があり、緊急を要する場合もあるので、心の準備だけはしておきましょう。
おでこや頭を冷やす
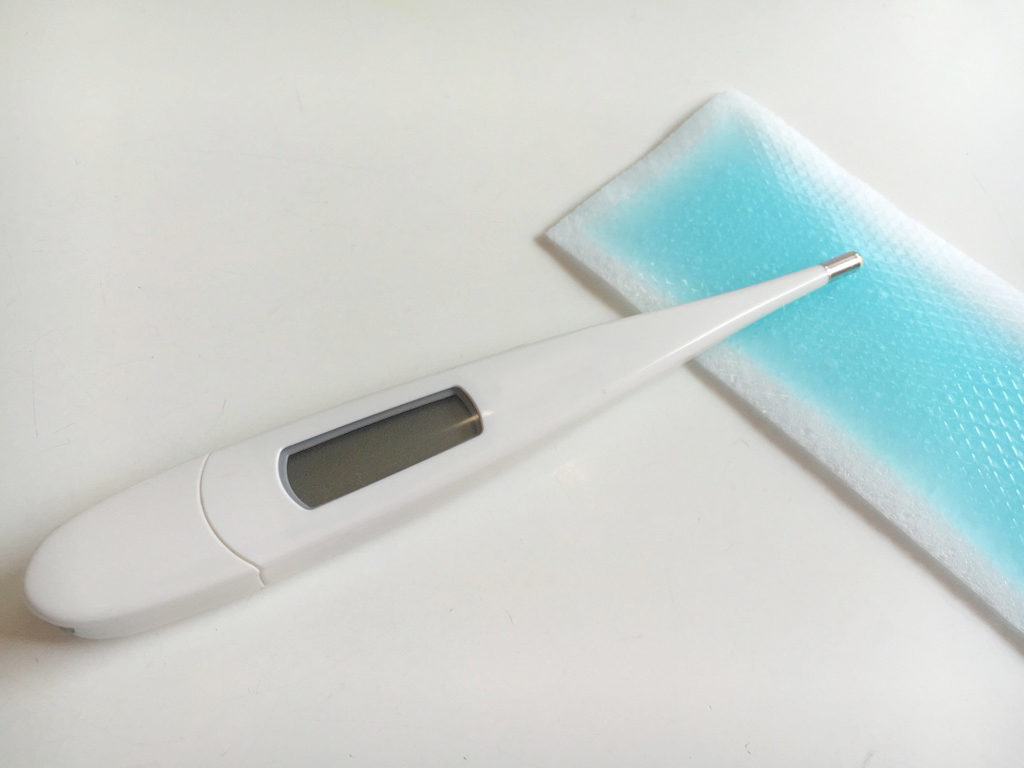
発熱の時には、大人は冷えピタなどの熱さまシートなどでおでこや頭を冷やします。
赤ちゃんにもしたほうがよいのかなと迷う人も多いようです。
赤ちゃんが嫌がる場合などは、無理におでこを冷やす必要はありませんが、赤ちゃんが気持ちよさそうであれば冷やしてあげるとよいでしょう。
小さな保冷剤をタオルやガーゼにくるんで冷やしてあげる、タオルを濡らしておでこにあてる、子ども用の熱さまシートを貼ってあげるなど、赤ちゃんの様子を見ながら対処してあげてください。
おでこ以外にも、太ももの付け根や両脇に挟むのも効果的です。
水分補給とこまめな着替えをさせる
発熱の際には、たくさんの汗をかきます。
赤ちゃんの体は脱水気味になるので、こまめに母乳やミルク、白湯などで水分を補給させてあげましょう。
水分を受け付けない場合もありますね。
全く飲んでくれない場合は、病院に相談し、再度受診したほうがよいでしょう。
また、たくさんの汗で、衣服が濡れてしまい、そのままにしておくと、冷たくなりさらに体調が悪化してしまったり、あせもや湿疹ができてしまったりします。
着替えも、赤ちゃんの寝ているそばに何着か準備しておき、おむつを替えるタイミングなどで、こまめに着替えさせるように心がけましょう。
お風呂にいれても大丈夫?
赤ちゃんの発熱時に、お風呂にいれるかどうか悩みますよね。
病院に行ったのであれば、そのときに聞いてみると良いのですが、そうでない場合はどうすればよいでしょうか。
赤ちゃんの機嫌が良ければ、軽くお風呂で汗や汚れを落としてあげてもよいでしょう。
しかし、浴槽に長く浸かってしまうと、その分体力も消耗するので、さっと短い時間で済ますようにしてください。
赤ちゃんが嫌がる場合は、元気がないときには、温かいタオルで体を拭く程度にしておきます。
また、お風呂上りに身体が冷めてしまわないように、脱衣所は温めておいてくださいね。
外出しても大丈夫?
「熱が38度前後あるけど、元気も食欲もあるから外出しても大丈夫?」
と、外出の予定が入っていてどうするか迷う時もあります。
しかし、赤ちゃんは免疫力が弱いので、ご機嫌でいたとしても、外出先で別の感染症やウイルスをもらってしまうかもしれません。
赤ちゃんの熱が下がるまでは、できるだけ家の中で過ごすようにしてください。
高熱や風邪の時におすすめの離乳食

高熱や病気の時の食事は、食べない赤ちゃんもいるので、無理に食べさせる必要はありません。
ミルクや母乳だったら飲むという場合には、そちらの比重を多めにしてもよいでしょう。
また、離乳食中期であれば、飲みこみやすいように離乳食初期のものを作るなど、ワンステップ前にずらして離乳食を作ると食べやすいと思います。
レンジで茶碗蒸し
〇材料
お味噌汁50㏄、お湯50㏄、お味噌汁の具大匙1、溶き卵4分の1個
〇作り方
大人用のお味噌汁とお湯をまぜ耐熱容器にいれます。具材は細かく刻む・潰します。
具材と溶き卵も入れてまぜ、ラップをかけてレンジで30秒加熱して完成です。
かぼちゃスープ
〇材料
かぼちゃ4分の1個、玉ねぎ4分の1個、調整したミルク100㏄
〇作り方
かぼちゃと玉ねぎを小さく刻み、柔らかくなるまで茹でます。
茹でたものをミキサーにかけ(つぶしても大丈夫です)、できたものの大匙2を、
調整したミルクを混ぜ合わせて完成です。
残ったかぼちゃと玉ねぎは、牛乳と塩コショウ、コンソメで味付けし、大人用のポタージュにしましょう。
野菜たっぷりにゅうめん
〇材料
そうめん10本、ホウレン草や人参大匙1、だし汁150㏄、醤油小匙3分の1
〇作り方
そうめんを茹でてみじん切りにします。小鍋にそうめんと細かく刻んだ野菜、だし汁を入れて煮ます。
醤油で味付けをして完成です。
色々なメニューがありますが、基本的にはさっぱりとしたとろみのあるものが食べやすいでしょう。
おかゆやうどん、ゼリー、すりおろしたリンゴ、バナナなどもおすすめです。
比較的赤ちゃんのご機嫌が良い時や落ち着いているときに、一口ずつ食べさせてあげましょう。
まとめ

赤ちゃんのお世話で、夜中も泣いて寝ない日が続くかもしれません。
赤ちゃんが寝ているときは、お母さんもできるだけ身体を休めてくださいね。
まずは、赤ちゃんの急な発熱や高熱に慌てないことが大切です。
そのあとは赤ちゃんの様子をしっかりとみて、何か熱以外の症状がないか確認しましょう。
何か気になることがあれば、メモしておき、受診の際に伝えるとよいですね。
対処法や離乳食などご紹介してきましたが、何か参考になるものがあれば嬉しいです。