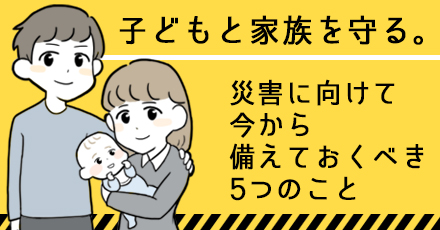だいたい1~2歳くらいからトイレトレーニングをスタートしますよね。
トイレトレーニングの大きな壁のひとつに「便座」があります。
大人用の便座にすんなり座る子と嫌がって座らない子がいるんです。
この記事では、大人用の便座に座る子に準備してあげたい補助便座と、便座に座らない子のトイレトレーニングの進め方を筆者の経験談を交えて次のような項目で紹介しています。
・トイレトレーニングのスタートは大人が使い方を見せること
・便座に座る子には、補助便座を準備し、自力でできる環境を整えてあげよう
・便座に座らない子は補助便座になるおまるを使うのがおすすめ
・おまる~便座にステップアップする方法と、おすすめのおまる
・おまるの後処理が楽になる方法
・トイレは便利になると怖くなる!
いつかは終わるトイレトレーニングですが、できるだけ早く便座でできるようにしたいですよね。
子どもに合わせた補助便座やおまるの使い方を見ていきましょう!
目次
トイレトレーニングは大人が使い方を見せるところからスタート!

トイレトレーニングのスタートは、まず、大人が使い方を見せるところから!
トイレに入っている姿を子どもに見せるのは嫌、と感じる方もいますよね。
でも、1~2歳児は言葉で説明しても理解できません。
実際に目で見て、体験することで使い方を覚えていきます。
1~2歳児は、ママの姿が見えなくなると不安になってしまう子も多いもの。
ですから一緒にトイレに入ってみましょう。
・「ママ、トイレに行くね」と話しかける
・「今、おしっこしているのよ。トイレでおしっこしようね」とトイレのことを説明する
・「トイレがおわったら、ティッシュで拭いて流そうね」と処理の仕方を教える
・「トイレの後は手を洗おうね」手を洗う様子を見せる
こうしたことを、毎日、続けて見せてみましょう。
そうすれば「トイレでおしっこをする」ということが子どもの頭にインプットされます。
毎日続けるのがコツですよ。
便座に座る子には補助便座で使える環境を作ってあげて

大人がトイレを利用している様子を見て「私もやりたい!」と直ぐ真似をする子がいます。
そして、すんなりと便座に座り、成功!という子も。
筆者の下の子がそうでした。
上の子のトイレトレーニングに苦労している横で、1歳過ぎから便座に座り、1歳6か月にはおむつが外れました。
親と姉のトイレの様子を見ただけでトイレトレーニング終了です。
自分から便座に座る子のトイレトレーニングのコツは、便座を使える状態にしておくこと。
踏み台を置き、補助便座を設置して、子どもがいつでも自分一人で安全に使える環境にしておきます。
大人が排泄する時に補助便座を外さなければならないという手間はありますが、補助便座を設置したままにしておけば、子どもは「自分でトイレに行ける!」という達成感を味わえます。
便座に座る子のトイレトレーニングの時は、ステップや踏み台と補助便座を準備して環境を整えてあげましょう。
便座に座らない子は補助便座になるおまるを使おう

さて、困るのが便座に座らない子のトイレトレーニング!
筆者の上の子がそうでした。絶対に便座に座らないんです。
保育園の子ども用便座には座りますが、排泄できず、家の大人用の便座は断固、拒否!
便座に座らない子は、おまるを使いましょう。
それも補助便座になるおまるです。
そして、確実におしっこが出る時におまるに座らせて「おまるでおしっこ成功!」を体験させます。
<おまるの使い方>
【設置場所】リビングや子ども部屋など、いつも遊んでいる慣れた場所
【使う時間】寝起きやご飯の後、入浴前など、必ずおしっこが出る時間
【座らせ方】「お座りしようか~」というように、自然に誘う(無理強いしない)
オモチャやお菓子で誘ってもOK!
とにかく、一回、成功させて、これ以上にないほど大袈裟に褒めてください!
成功した時にお菓子を食べさせても構いません。
とにかく、おまるで排泄できたら、一歩前進です。
筆者の子は、服を脱いでお風呂に行くとおしっこが出ていました。
浴室の体を洗う場所でいつもおしっこしちゃうんです。
ですから、浴室におまるを設置!
服を脱いだら直ぐ、おまるに座らせておしっこ成功!
その場でめちゃくちゃ褒める!を繰り返しました。
おしっこはおまるでする。
これをしっかり覚えてもらいましょう。
おまる~便座へステップアップする方法(経験談)

必ずおしっこが出る時間におまるを使い、おまるでおしっこができるようになったら、おまるをトイレに移動させます。
そして、トイレという空間に慣れてもらいましょう。
トイレの中で、おまるでおしっこができたら、めちゃくちゃ褒めてください。
それから、おしっこをトイレに流します。
水が流れる音が大きくてビックリする子もいますから「今から流すね。おしっこバイバ~イ!」というように、ママが説明して親子でバイバイしてみてください。
トイレという空間に慣れ、水の音にも慣れたら、次はトイレの便座に座ります。
おまるを補助便座にしましょう。
これまで使っていたおまるが便座になっているので、子どもの抵抗感も和らぎます。
補助便座に座い、踏み台に足を乗せて足が地に着いた状態で排泄させましょう。
そして、子どもが便座から降りた後、流します。
絶対に子どもが便座に座った状態で水を流さないでくださいね。
おしりの下で、突然大きな音がしたら子どもはビックリして恐怖を感じます。
トイレ=怖い!になるとトイレトレーニングはやり直しに!
必ず子どもを便座からおろし、子ども自身に子どものタイミングで流してくださいね。
おすすめのおまる

おまるを選ぶ時のポイントは、補助便座になる・手すりがある・飛び散り防止の3つ!
少々、邪魔になりますが、便座を嫌がって座らない子には補助便座になるおまるを買ってあげてください。
自分の意志でトラウマなくステップアップするために必要なグッズです。
<おすすめおまる>
【アガツマ アンパンマン 5WAYおまる おしゃべり付き】(ASIN/B00M7VAYAG)
補助便座になるおまるで、アンパンマンがおしゃべりしてくれます。
排泄中に掴まる手すりがあり、飛び散りも防止してくれる設計になっているのでお勧めです。
【ベビーロディおまる】(ASIN/B00VPYE4JS)
イタリアの会社が作っている馬を模した玩具ロディのおまるです。
ロディ=またがるものなので、嫌がらずに座る子も多いはず!
補助便座になり、手すり付きで飛び散りも気にならないタイプなのでいいですよ。
【HIヒロセオリジナル トイレ用踏み台 すっきりステップ】(ASIN/B0795D13KF)
トイレトレーニングの時には必ず準備したい踏み台。
便座に座る時だけでなく、排泄する最中も足が地に着いている方が落ち着きます。
お腹に力を入れて息むときに踏み台は欠かせません。
【Acko 折り畳みスツール】(ASIN/B079DKY473)
「トイレトレーニング後、踏み台が不要になるのでは?」「トイレが狭くて物を置きたくない」という方は、折りたたみ式プラスチック製の踏み台を使ってみてください。
トイレトレーニングが終わったら持ち運びできる踏み台として使ったり、運動会などの行事でスツールとして使うといいですよ。
おまるの後処理が楽になる方法

おまるは便座に座らない子に便利ですが、億劫なのが排泄物の処理!
なんとか楽に処理したい、という方はペットシーツを使ってみてください。
おまるの中に予めペットシーツを折りたたんで設置しておけば、おしっこをしっかり吸収してくれるので簡単に処理が可能!
なお、おまるとペットシーツは万が一の災害の時にも使えます。
断水したり停電したりしてトイレが使えなくなった時でも、排泄物の処理ができますから、ストックしておくといいですよ。
トイレはどんどん怖くなっているから要注意!

筆者がトイレトレーニング中に非常に困ったのは、商業施設に設置された進化したトイレです。
買い物などで利用した時、便利なトイレに入ったことで何度もトイレトレーニングが中断した苦い経験が!
<進化したトイレの特徴>
・人を感知してフタが自動で開く
・人を感知すると青く光りながら自動洗浄する
・人が立ち上がると自動で水が流れる
・人が座ると、水が流れる音が流れ出す
こうした機能は大人にとっては便利なのですが、子どもからすると
「誰も居ないのに、勝手にトイレが動き出した!」
「目が光ってるみたい!」
「まだ座っているのに水が流れた!」
このような恐怖の対象になるんですね。
トイレは大人の体に合わせて設計されています。
ですから、小さな子どもが利用すると思わぬ時にセンサーが働いて突然、水が流れたり音が出たりします。
やっとトイレに慣れて排泄できるようになったと思ったら、外出先のトイレで「怖い!トイレ嫌い!」になり、一からやり直し……。
便座が嫌い!怖い!という子のトイレトレーニングは、外出先も要注意です。
なお、多目的トイレや子ども用トイレの便座には、自動機能が付いていないことが多く、子どもも怖がらずに使えて助かりました。
トイレトレーニング終了までは、出先のトイレ事情把握が欠かせません。
まとめ

トイレトレーニングは、まず大人が使い方を子どもに見せるところからスタート。
トイレトレーニングがスムーズに進む子の場合は、補助便座や踏み台を準備してあげることで自力で便座を使えるようになります。
便座に座らない子やトイレを嫌がる子は、まず、おまるで成功させるところからスタート!
次にトイレでおまるを使い、トイレという空間に慣れてからおまるを補助便座にして便座に座ってみましょう。
小さな成功を積み重ねていって、便座でできるようにしていきます。
ただ、トイレトレーニング中は外出先のトイレに要注意!
自動機能が思わぬタイミングで機能し、子どもがトイレを怖がるようになることも。
トレーニングが終わるまで大変ですが、子どものタイプに合わせて便座でできるようにしていきましょうね。